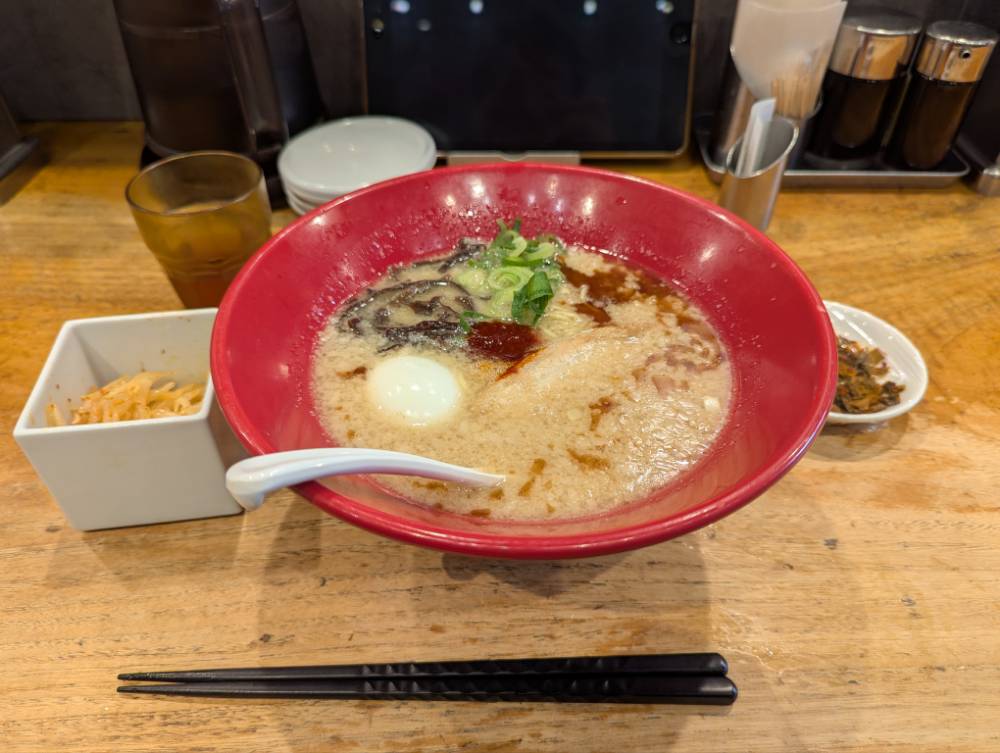幕張出張2025 – インフラ研修完了!

アパホテル8泊9日、割り当てられていたインフラ研修の全日程が完了いたしました。
私の担当は初心クラスのため「OSI参照モデル」という用語も、はじめまして! という新入社員ばかりのクラスです。
テキストは、TCP/IPの話から、CISCOルータの設定方法、NAT・NAPTまでと盛りだくさんで、AWSでVPCを作成してEC2インスタンツを起動させ、Linuxも触るというけっこうハードスケジュールな内容でもありました。
ただ、その方面の会社であればこのくらいやっておかないと、ではあるので、習熟度を確認しながら、お客様指定のカリキュラム通り、無事に最後まで進めることができました。
日報を眺めていると、きれいな正規分布の習熟度です。これならば、講師の務めとしては及第点でしょう。
そして今回の研修で気づいたことがあり、それをメモしておこうと思います。
社会人研修は、組織力の向上が正義
- 個人スキルの底上げはいいけれども、組織力向上には直接紐づかない
- 組織力向上は、ある特定の演習をグループで解いてもらうことが一番作用がある
- 個人スキルの底上げをするためには、同じ目標を持たせて共有しあう必要がある
ここから先は、自分の中でじわじわ効いてきた「気づき」なので、まだうまい言語化ができていないのですが、今回、改めてこう思いました。
ああ、自分が「良かれ」と思っていた指導方法は、もしかしたら組織にとって「正解」じゃないのかもしれない、と。
Udemy でも私は何本か講座を出していますが、たとえば Excel のスキルが個人単位で向上しても、それだけでは組織全体の力になりません。むしろ「個人の成長」が点で終わってしまって、他者と繋がらないまま孤立するケースもあるのではと考えました。
- スキルを上げて楽をしたい
- 同僚と差をつけて安心したい
- 人事が言うから、さっさと覚えたい
実は、この要望をサポートしてしまっている気がしたのです。
だから、レビューの満足度が高くなる。レビューというものがあるゆえに、そっちをどうしても攻めてしまう。わかりやすく、やさしく教えることはもちろん大事。だけれども、それだけでは「線」や「面」にはならない。
組織として強くなるには、同じ目標を共有し、協力して乗り越える経験が必要であり、グループワークにはその要素が詰まっているんだな、と強く感じました。
最終日のグループワークは、本当に新入社員の成長を見ることができました。
個人の操作力を高めるだけでなく「チームで成果を出す」という体験もあわせて設計していく。そういう講座構成にしていかないと、その研修は会社のためにならないと考えました。
もちろん、個別研修はこれまでどおり、個人のスキルアップのために指導は続けます。ただ、企業研修はちょっと思考を変えていきます。
ああ、なんで気づかなかったんだろう。
今回の8泊9日、カリキュラムを完遂できたことよりも、この気づきこそが、一番の収穫でした。頭の中では、まだ明確な整理はしきれていませんが、この実感を大切に、また次の研修に臨んでいきます。